はじめに
確かに、慌ただしい毎日の中、本を読むのはなかなか難しいですよね。
「月1冊も本を読まない人が6割いる」という情報も聞いています。
昨今、速攻で消費できるジャンキーなコンテンツが爆増しており、じっくりと読み進めなければならない書物は敬遠されがちです。
また、活字の羅列そのものに嫌悪感を示される輩もいます。
「本くらい読まないとなぁ」と思いながら、つい謎のコンテンツをジャブジャブ浴びてしまいます。
困ったものです。
【問題】
読書嫌いを克服し、本を読めるようになりたいんだが?

本記事を読み、読書への苦手意識の原因を特定し、読書のメリットを確認すれば問題ありません。
さらに、読書のハードルを下げる方法までゲットし、余裕で活字の海を爆泳ぎできるようになります。
では、始めます。
【理由1】読書への苦手意識の原因を知れば問題ない
まずは、読書への苦手意識の理由を確認することです。
言います。
読書ヘイト 理由 一覧
・入口が教科書の文学作品である
大半の人間の本格的な読書デビューは、国語の教科書にある謎の文学作品です。
教科書掲載の物語が悪いわけではないですが、エンタメ性やギャグ線は終わっており、教育的価値や文学的評価に重きを置いています。
一般社会の道徳から外れていたり、常識に対する批判が含まれていたり、娯楽性を多く含む作品は、教科書の選抜メンバーにはなれません。
そのため、役に立つでもワクワクするでもない、捨て曲のベストアルバムのような仕上がりになります。
少なくとも、人生経験1ケタのキッズが味わうには少々味付けが繊細過ぎます。
言葉を選んで言うと、つまらないです。
このせいで、「よく分からない」「意義を感じない」「堅苦しい」「活字キモい」というネガティブなイメージが形成される場合があります。
ここだけの話、純文学は読書の中でも上級者向けに位置します。
比喩や暗示などの文学テク、深い人間洞察、こねくり回した表現などが凝縮された、こちらに理解・教養を要求する芸術作品です。
こんなものを1stステージに置くのは、やや攻めすぎのきらいがあります。
早々に「読書=文学作品」のイメージを植え付けられるのは、悪影響が大きいと思われます。
・自分で読み進めないといけない
動画や音楽などのコンテンツは、再生ボタンをポチればあとは自動で流れていきます。
いわばエスカレーターのようなもので、こちらから動かずとも強制スクロールでゴールへ迎えます。
しかし、活字は勝手に動いてくれず、こちらで読み進めないと入ってきません。
いわば階段のようなもので、能動的なぶん、読書はカロリーを消費します。
さらに、読書は「ながら消費」ができません。
読書しながら何かできるのはカカシ先生くらいで、常人は本に全集中する必要があります。
人間は、とにかくできる範囲で怠けようとする生き物です。
受動的コンテンツが充実する今、どちらに流れるかは明白であります。
ご覧の通り。
繰り返しになりますが、ご覧のとおりであります。
【理由2】読書のメリットを知れば問題ない
次に、読書のメリットを認識することです。
得だと分かればいけます。
読書 メリット 例
・深い知識を得られる
これに尽きます。
本の知識は、有益で信憑性も高いです。
なぜなら、本の情報は、出版までの厳格なプロセスを通過した精鋭ぞろいです。
出版社は会社のブランドを賭けてガチで売りにきていますし、作者も名前(場合によっては顔面)を晒して退路を断っています。
本として流通している時点で、すでに修羅場をくぐり抜けており、面構えが違います。
特に名著と呼ばれるものの効果は甚だしく、大げさでなく人生を変えます。
先人たちが己の人生で得た知見を1000円~2000円程度で頂戴できるのですから、そのコストパフォーマンスは群を抜きます。
人の一生のフィールドワークで実際に触れられる知識なんざ、ミジンコのようなものです。
あまりに我々は無知なのです。
金持ちになるほど、読書を習慣にしている傾向があるそうですが、シンプルに、書物の力を借りて知識をつける方が強いということです。
・語彙力、表現力の向上
文章にたくさん触れれば、それだけ言葉のストックが増えます。
脳みそでどれだけ上等なことを考えようが、豊かな感受性を持っていようが、「うんこ」という言葉しか知らなければ、全てが「うんこ」として出力されることになります。
気持ちや思想と言った形のない概念は、知っている言葉でしか表現できません。
なので、できるだけいろんな言葉を操れた方がいいでしょう。
特に意識しなくても、本をたくさん読んでいく中で、脳は気になった言葉をそっと引き出しにしまっていきます。
自分の感性が選んだオリジナルの辞書が脳内に出来ていくので、問題ありません。
ご覧の通り。
他にもたくさんありますが、意識するのはこれくらいがいいでしょう。
【理由3】読書のハードルを下げれば問題ない
最後に、具体的な読書をラクにする方法です。
見せます。
らくらく読書 方法 例
・電子書籍にする
最大のメリットは、寝っ転がりながらスマホ片手で読めることです。
紙の本は腕が疲れるし、寝転ぶと光が当たらず暗いので、無理です。
さらに、フォントや文字サイズ、行間もカスタマイズできます。
明朝体が堅苦しいならゴシック体にチェンジし、行間も広げれば異常に読みやすくなります。
・「読書=小説」のイメージを捨てる
「読書=小説」のイメージがなんとなく強いですが、小説はかなり人を選ぶ娯楽です。
好きな人は好きですが、看板役を張らせるほど万人ウケするもんじゃないです。
文字オンリーは想像力のコストがかかるので、物語を楽しむなら映像作品の方がいいという人が多いと思います。
興味ないやつが「本くらい読まなきゃ」と小説を買って無理やり読むと、得られるものは疲労とストレスです。
「読書=知識獲得」と捉えて、実用書・知識本をメインに攻めれば問題ありません。
なんでもいいので興味のあるジャンルの本を買って、知識欲が満たされたり、人生の役に立ったと実感する体験ができれば、いけます。
ご覧の通り。
ここまでの文章を読めたのなら、読書もいけます。
まとめ
読書の苦手意識は、教科書の謎の文学作品による初見殺しや、能動的なエネルギーが必要とされる点にあります。
しかし、本を読んで、己の守備範囲外の知識を得ることは、人生を豊かにするうえでとても大事です。
まずは、日々ネットで調べるようなことを、ネットショップの検索欄に打ち込み、気になった本を電子書籍で購入すれば問題ありません。
寝っ転がって尻をかきながら、ゴロゴロするノリで本に向かえばいけます。
師匠曰く――
「本読んだら、動けよ」
確かに、本を読んで興味や好奇心を広げ、実際に行動に移すと、さらに人生エリアが拡大します。
本は終着点ではなく、今の自分と新しい自分を繋げる架け橋であります。
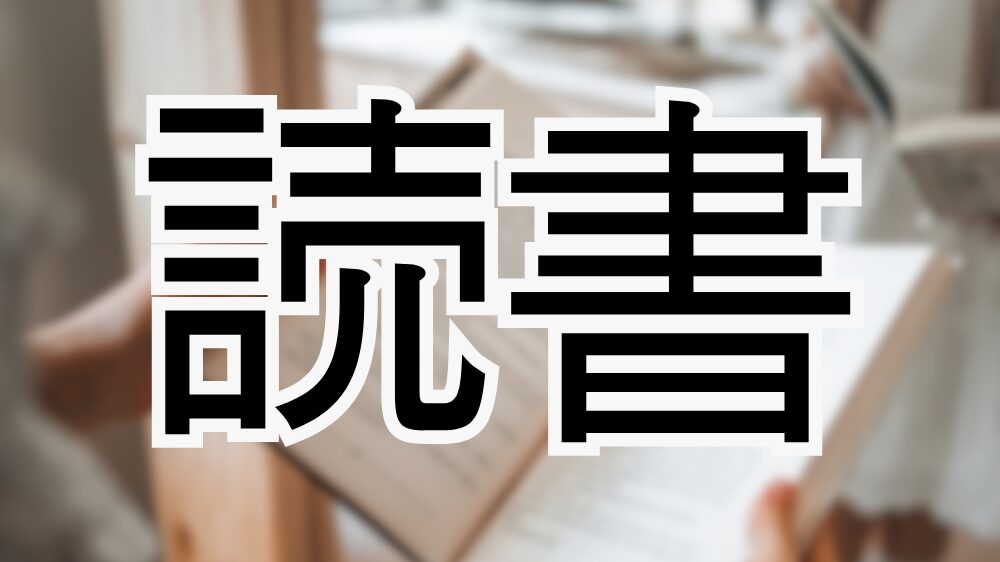


【結論】
なるほど。大丈夫です。